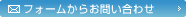Q&A
2013年4月1日 月曜日
異母兄弟(姉妹)の相続分【再掲】
最近、お問い合わせが多いので再掲します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【異母兄弟(姉妹)の相続分】
民法では、 遺言がない場合の相続分を定めています。
これを「法定相続分」と言います。
それぞれ取得する相続分は、以下のとおりです。
①子と配偶者が相続人の場合
→ 子が2分の1、配偶者が2分の1(配偶者が死亡している場合、子がすべて相続)
②父母と配偶者が相続人の場合
→ 配偶者が3分の2、父母が3分の1(配偶者が死亡している場合、父母がすべて相続)
③兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合
→ 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(配偶者が死亡している場、兄弟姉妹がすべて相続)
優先順位は、①→②→③の順番です。
子供がいる場合は、父母は相続人になりません。父母がいる場合は、兄弟姉妹は相続人になりません。
さて、子供も両親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になりますが、この兄弟姉妹に「異母兄弟(姉妹)」がいる場合はどうでしょう。
異母兄弟も、相続人になります。
しかし、異母兄弟(姉妹)の相続分は、父母ともに同一とする兄弟姉妹の「2分の1」です。
例えば、亡Aさんの相続人が、Aさんの配偶者B、Aさんの弟C、Aさんの妹D、そしてAさんの父親の前妻との子供Eの4名としましょう。
それぞれの相続分は、
B(配 偶 者):4分の3 → 20分の15
C(兄弟姉妹):4分の1×5分の2 → 20分の2
D(兄弟姉妹):4分の1×5分の2 → 20分の2
E(異母兄弟):4分の1×5分の1 → 20分の1
と、なります。
異母兄弟(姉妹)などは、なかなか連絡しづらいですよね。
遺言を書いておかないと、兄弟姉妹がストレスを抱えることになるので、お気を付けください。
投稿者
最近のブログ記事
- 司法書士の横領事件から考えること ― 信頼と制度、そして人間の現実 ―
- 不動産登記に詰め込まれる社会 ――増え続ける情報と現場の現実
- 静かな循環の中で― 年の終わりに、司法書士としての感謝を胸に ―
- 対立がなぜ起きるのかをAIに聞いてみた―箱を回して世界を見る―
- 土地と安全保障──日本における防衛目的の土地利用をめぐって
- 国籍記載を義務化へ ―― 日本の不動産市場と経済安全保障の新しいかたち
- 信じる者は救われ…ないかもしれない ー広告社会をAIで透かして見た日常ー
- 時代の波と事業の終焉:2025年ピーク後の日本の「事業の出口」
- 公正証書のデジタル化が始動 —手続きが暮らしに寄り添う時代へ
- 司法書士が直面する情報提供の葛藤 ―相続人の要望と秘密保持義務のはざまで―