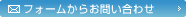2013年4月18日 木曜日
法人か個人事業主かの選択
個人事業主の方が、法人化したほうがいいかどうかの選択について。
細かいことを言えば支払う税金の違いなどの話もありますが、「仕事」というものをどういうスタンスで取り組むかで選択したほうがいいと思います。
自分の経験知識を活かして「プレイヤー」として仕事をするならば、個人事業主でいいと思います。
一方で、法人化のメリットは、個人ではなく会社に信用・ブランドがつくことです。
・従業員を使って、複数の人で一つの「ブランド」を使って仕事をする
・自分は社長として「マネジメント」をする(プレイヤーは従業員)
このような状況ならば、法人化すべきだと思います。
人を雇うならば、自分がリタイアした後のことも考える必要があるでしょう。
会社に信用・ブランドがついていれば、自分の作った会社は自分が死んだ後も続きます。
逆に言うと、法人化しているのに社長個人の信用やブランドで仕事をしている会社は、社長がリタイアしたら潰れます。
そういう会社は、社員全員が共有できる経営理念などを作るなどして、早く会社に信用を移してください。
自分はプレイヤーなのか、マネージャーなのか、どういう人とどういう環境で仕事がしたいのか、そういう視点で考えた方が、自分の方向性やブランディングも明確になると思います。
投稿者 | 記事URL