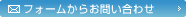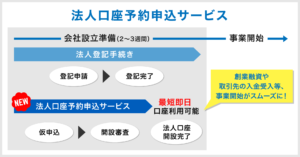2025年7月8日 火曜日
本家の嫁が背負う祭祀と遺産の不均衡:法と慣習の狭間で
本家の墓を守る立場に置かれながら、遺産は一切承継しなかった、という話を聞くことがある。たとえば、夫に先立たれた長男の妻が、義父母の介護を行い、葬儀や法要を取り仕切ってきたにもかかわらず、相続人ではないため、遺産分割協議には関与できず、何の財産的利益も受けなかったケースである。その一方で、墓地の管理や仏壇の維持といった祭祀に関する責任だけは、慣習的に引き受けるよう求められたという。
このような状況は、法制度上も説明がつく。民法897条は、系譜・祭具・墳墓の承継、すなわち祭祀財産の承継について、次のように定めている。
まず、地域や家の慣習に従うこと。慣習が明らかでない場合には、被相続人の指定によること。指定がなければ、家庭裁判所が決定することになる。そしてこの祭祀承継者は、必ずしも法定相続人である必要はない。
したがって、血縁関係のない「本家の嫁」であっても、祭祀承継者になることはあり得る。長年にわたり家の宗教的・儀礼的行事を担っていたことが評価されれば、なおさらである。

一方で、相続財産の承継については民法の規定に従う。相続人に該当しない者が遺産を受け取るには、被相続人の遺言や死因贈与契約などによる明示的な意思表示が必要である。それがなければ、法定相続人による協議で財産が分配され、相続人以外の者は除外される。
この構造により、遺産を受け取ることはできないが、祭祀の義務だけは引き受けるという状況が生じ得る。墓地の使用料や管理費、定期的な供養の手配といった負担が、祭祀承継者にのしかかることになる。
制度的には、祭祀財産と相続財産が別の原理で承継されるため、こうした事例は法的に矛盾しているわけではない。しかし、当事者にとっては、承継と報酬、責任と権利の関係が不平等に感じられる場面がある。
このような問題を回避するには、あらかじめ遺言などで明確な意思を示すことが有効である。祭祀を託したい相手に対して、相応の財産を渡す意向があるのであれば、それを文書に残す必要がある。また、関係者間での事前の合意形成も望ましい。
最近は墓じまいをするという話も聞くが、まだしばらくは残る問題だろう。制度と現実の乖離は、どの社会にも存在する。法的には正当であっても、当事者に不満や疑念が生じることは避けがたい。そうであるからこそ、制度の隙間を見据えた対応が求められる。
投稿者 | 記事URL