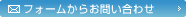Q&A
2025年10月25日 土曜日
時代の波と事業の終焉:2025年ピーク後の日本の「事業の出口」
いま、日本の中小企業は「経営者の高齢化」という避けられない変化の波の中にある。
過去23年間で経営者の年齢のピークは47歳から69歳へと大きく上がり、小規模事業者では平均引退年齢がすでに70歳を超えている。
かつて主流だった親族内承継は4割以下にまで減少し、後継者不在という壁に直面する企業が増えている。
こうした背景のもと、休廃業や倒産といった「企業の退出」が2025年にピークを迎える可能性が高いとみられている。
その理由は、大きく二つの圧力が同時期に集中するためだ。

- 高齢化という“時間の壁”
まず、デモグラフィー(人口構造)の面での集中がある。
戦後の経済を支えた団塊の世代(1947~1949年生まれ)が、2025年に75歳という後期高齢者の節目を迎える。
この年齢は健康上のリスクも高まり、事業を「続けるか」「たたむか」を決断せざるを得ない時期にあたる。
まさに時間がもたらす“経営の終着点”がそこにある。
- 経済的なコスト圧力の重なり
次に、経済的な負担の増加だ。
最低賃金の引き上げは体力の小さい中小企業には大きな痛手となり、さらにコロナ禍で導入された金融支援策の元本返済も本格化している。
こうしたコスト圧力の中で、経営者は「損失をこれ以上広げない」ための合理的な判断として事業を終了させるケースが増えている。
実際、帝国データバンクの調査によると、2025年の休廃業・解散件数は年間7万件を超える見込みで、過去最多を大きく更新する勢いだ。
そのうち64.1%が、倒産ではなく手元資金に余裕があるうちに自ら幕を引く「資産超過型」の“余力ある廃業”とされている。
これは、経営者が冷静に状況を見極めていることの表れでもある。
ピーク後のゆくえ:高止まりする企業退出
では、2025年のピークを越えた後、企業退出の流れはどうなっていくのだろうか。
専門家の分析では、一時的に減少する可能性はあるものの、長期的には高い水準で続くとみられている。
その根本には、やはり高齢化という構造的な問題がある。
現在の社長の平均年齢は60.7歳と過去最高を更新し続けており、社長交代率は依然として低迷している。
経営者の若返りは進まず、事業承継が追いついていないのが現状だ。
さらに、団塊世代の引退後も、日本社会は高齢者人口のピークと労働力不足が重なる「2040年問題」へと向かう。
若い世代の人口減少により、後継者を見つけられず廃業を選ぶ企業は今後も多いと予想される。
また、最低賃金や社会保障費の上昇など、コストプッシュの圧力も続く。
結果として、収益が伸び悩む企業は事業継続の判断をさらに難しくしていくことになる。
今後に向けて:承継への転換が鍵
こうしたデータが示すのは、2025年の「退出ラッシュ」が一時的な出来事ではなく、
日本経済の構造が大きく変わる転換点であるということだ。
経営者たちは、事業を続けるよりも資産を守ることを選び、静かに幕を下ろしている。
それは必ずしも悲観すべきことではなく、「合理的な撤退」としての新しい時代の姿でもある。
とはいえ、この流れを少しでも前向きなものに変えるには、
「廃業」ではなく「承継」という選択肢を取りやすくする仕組みが欠かせない。
M&Aや第三者承継への抵抗感を減らし、「余力ある廃業」を「余力ある承継」へと転換する支援策が求められている。
特に、地域の産業や技術、職人のノウハウなど、時間をかけて築かれた財産が失われないようにすることが重要だ。
事業の連続性をどう守るか──その問いに、社会全体で向き合う時期が来ている。
投稿者
最近のブログ記事
- 不動産登記に詰め込まれる社会 ――増え続ける情報と現場の現実
- 静かな循環の中で― 年の終わりに、司法書士としての感謝を胸に ―
- 対立がなぜ起きるのかをAIに聞いてみた―箱を回して世界を見る―
- 土地と安全保障──日本における防衛目的の土地利用をめぐって
- 国籍記載を義務化へ ―― 日本の不動産市場と経済安全保障の新しいかたち
- 信じる者は救われ…ないかもしれない ー広告社会をAIで透かして見た日常ー
- 時代の波と事業の終焉:2025年ピーク後の日本の「事業の出口」
- 公正証書のデジタル化が始動 —手続きが暮らしに寄り添う時代へ
- 司法書士が直面する情報提供の葛藤 ―相続人の要望と秘密保持義務のはざまで―
- AIでの文字起こしが成年後見の現場で大活躍