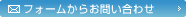Q&A
2025年10月13日 月曜日
公正証書のデジタル化が始動 —手続きが暮らしに寄り添う時代へ
これまで、公正証書を作るには平日昼間に公証役場へ行く必要があった。仕事の合間をぬって出かけ、印鑑証明を取りに役所へ寄る。実際にやってみると、なかなかの手間だ。「大事なことだから」と思いながらも、「しかし面倒だ」と感じてあきらめた人も少なくないだろう。私自身、依頼人とともに役場へ足を運ぶたびに「もう少し簡単になればいいのに」と感じてきた。
その不便を減らす仕組みが、ようやく動き出した。令和7年10月1日から、公正証書のデジタル化が始まった。

まず大きな変化は、申請がインターネットでできるようになったことだ。印鑑証明を取りに行かなくても、マイナンバーカードを使った電子署名で手続が完結する。紙の書類を抱えて役場へ行く必要がなくなるのは、実務を経験してきた者としても大きな前進だと感じる。
次に、リモートでの作成が可能になった点だ。公証人と画面越しにやり取りし、自宅や職場から内容の確認や署名ができる。体調や距離の問題でこれまで役場へ行けなかった人も、オンラインで同席できるようになった。関係者がそれぞれの場所から参加できるというのは、想像以上に心強い。
さらに、公正証書自体も電子データで作成されるのが原則となった。実印の代わりに電子署名を行い、完成した証書はデータで受け取ることができる。保管や共有が容易になり、「紙を失くしたらどうしよう」という不安からも解放される。
もちろん、リモートでの作成にはいくつか条件がある。利用者の希望、関係者全員の同意、公証人が適当と判断すること、そして法律で認められている手続であることだ。やや堅苦しく聞こえるが、要するに「本人の意思を確認し、安全に進めるためのルール」にすぎない。
完成した証書の受け取り方法も選べるようになった。紙でも、インターネット経由でも、記録媒体でもよい。電子データで受け取る場合には、パスワードを別の方法で伝えるなど、安全面にも配慮がなされている。また、養育費の取り決めや死後事務委任契約などでは手数料の軽減も予定されており、経済的な負担も軽くなる。
公正証書は、遺言や離婚、契約など、人生の節目に関わる大切な書類だ。不便さが理由で利用をあきらめてきた人がいたとすれば、その壁が取り払われる意味は大きい。
私自身も、依頼人とともに「これならできそうだ」と感じる場面が増えた。移動や時間の負担が減り、必要な制度が必要な人に届きやすくなる。制度が人の暮らしに寄り添う方向へ進んでいることを実感する。
ようやく、公正証書が「特別な人のための制度」から、「誰もが利用できる身近な仕組み」へと変わりつつある。
手続のハードルが下がった今こそ、公正証書の本来の価値、安心と信頼を形にする仕組みが、より多くの人に届く時代になった。
投稿者
最近のブログ記事
- 不動産登記に詰め込まれる社会 ――増え続ける情報と現場の現実
- 静かな循環の中で― 年の終わりに、司法書士としての感謝を胸に ―
- 対立がなぜ起きるのかをAIに聞いてみた―箱を回して世界を見る―
- 土地と安全保障──日本における防衛目的の土地利用をめぐって
- 国籍記載を義務化へ ―― 日本の不動産市場と経済安全保障の新しいかたち
- 信じる者は救われ…ないかもしれない ー広告社会をAIで透かして見た日常ー
- 時代の波と事業の終焉:2025年ピーク後の日本の「事業の出口」
- 公正証書のデジタル化が始動 —手続きが暮らしに寄り添う時代へ
- 司法書士が直面する情報提供の葛藤 ―相続人の要望と秘密保持義務のはざまで―
- AIでの文字起こしが成年後見の現場で大活躍