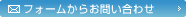ブログ
2025年11月21日 金曜日
国籍記載を義務化へ ―― 日本の不動産市場と経済安全保障の新しいかたち
東京都心の不動産価格は、長く住んできた人々ですら手が届きにくい水準まで上がっている。背景には、国内の需要だけでは説明できない大きな変化がある。海外からの投資マネーの流入が市場を押し上げ、それが日本人の生活実感とズレを生んでいる。この状況を受けて、政府は不動産登記に所有者の「国籍」を記載する制度の導入を本格的に検討し始めた。単なる事務手続きの変更ではなく、日本の不動産市場と経済安全保障の考え方が大きく転換しつつあることを示している。

■1 登記制度が抱えてきた“見えない所有者”という問題
これまでの登記制度では、所有者として記載されるのは「氏名」と「住所」だけだった。国籍は記載されず、国内に住民票を持つ外国人や、日本法人を通じて購入する外国資本も、日本人と区別がつかない仕組みだ。国交省はこれまで、住所が「外国にあるかどうか」だけを頼りに外国人の取得動向を推計してきた。しかし、これでは実態のごく一部しか見えてこない。
2025年上半期の調査では、新築マンションを取得した人のうち「住所が外国にある人」は3.0%だったとされる。ただし、この数字には日本に住み、普通に会社勤めをしている外国人や、外国資本のペーパーカンパニーが買った物件は含まれない。実際の外国人購入比率は、もっと高いはずだと言われている。
さらに、1年以内の短期転売が8.5%を占めたという結果もある。これは投機目的の資金が流れ込んでいるサインだ。本来「住むための場所」であるはずの住宅が、「短期間で売買して利益を得るための資産」へと変わりつつある。
■2 なぜ今“国籍情報”なのか:経済安全保障の観点
今回の政策の背景には、住宅価格の高騰だけでなく、日本全体の安全保障をどう守るかという、より大きな問題がある。近年、政府は「経済安全保障」という概念を広く捉えるようになった。
従来、重要施設の周辺だけが関心の対象だった。たとえば自衛隊基地や原子力発電所の近くの土地は、外国資本が取得すると安全保障上の懸念があるとされ、調査や規制の対象になってきた。しかし、現代の安全保障はそれだけでは守れないと考えられ始めている。
●都市部の住宅そのものが“国家の基盤”
日本では人口の多くが都市に密集して住んでいる。東京圏はその典型で、住宅を確保すること自体が「生活の安全保障」に直結する。外国資本による大量取得や、投機マネーによる価格高騰が続くと、国民が住む場所を確保できなくなる。それは軍事や外交の話とは別の意味で、「国としての安定性」を脅かすリスクにつながる。
安全保障を「国を守ること」と広く捉えるなら、人が安心して住める家が確保されない状況もまた、国家の弱体化を招くという発想だ。
●国際的には“生活基盤の保護”はすでに常識
世界を見れば、国籍によって不動産取得に制限を設ける国は少なくない。
-
シンガポール:外国人に高額の追加税(最大60%)
-
カナダ:一部地域で外国人の住宅購入自体を禁止
-
オーストラリア:外国人は購入前に政府の審査が必要
これらの制度は、国民の住宅確保を守るという意味で「経済安全保障」の一環として位置付けられている。日本の制度はむしろ異例で、これまでほぼ“完全に自由で、誰でも買える市場”だった。
今回の国籍記載義務化の動きは、日本が世界標準に近づく方向へ舵を切り始めたことを意味する。
■3 制度が変わると市場はどう動くか
法改正が進むまでには時間がある。この「空白期間」に市場では二つの動きが起こる可能性がある。
-
制度変更前に駆け込みで買う動き
匿名性を失いたくない海外マネーが、制度が変わる前に購入を急ぐ可能性がある。 -
逆に買い控えが増える動き
国籍が把握されることをリスクと見る層は、日本市場から一旦距離を置く可能性がある。
中長期的には、国籍データが蓄積されることで政策対応がしやすくなる。特定国の資金が特定地域に集中している場合は、そのエリアで追加課税を行う、といった選択肢も理論上は可能になる。
■4 “開放”と“防衛”のバランスをどう取るか
日本にとって難しい問題は、海外からの投資を拒むべきではない一方で、国内の人の生活を守る必要もあるという点だ。海外マネーが都市に流れることは、開発や経済成長の面ではプラスに働く。しかし、過度に集中すれば住宅価格を押し上げ、国民生活を圧迫することになる。
今回の政策検討は、こうした二つの価値の調整をどのように図るかという、深いテーマを含んでいる。
透明性を高めつつ、必要以上に外国人を排除しない。その中間点をどう探るかが、これからの日本の不動産政策の課題となるだろう。
投稿者
最近のブログ記事
- 司法書士の横領事件から考えること ― 信頼と制度、そして人間の現実 ―
- 不動産登記に詰め込まれる社会 ――増え続ける情報と現場の現実
- 静かな循環の中で― 年の終わりに、司法書士としての感謝を胸に ―
- 対立がなぜ起きるのかをAIに聞いてみた―箱を回して世界を見る―
- 土地と安全保障──日本における防衛目的の土地利用をめぐって
- 国籍記載を義務化へ ―― 日本の不動産市場と経済安全保障の新しいかたち
- 信じる者は救われ…ないかもしれない ー広告社会をAIで透かして見た日常ー
- 時代の波と事業の終焉:2025年ピーク後の日本の「事業の出口」
- 公正証書のデジタル化が始動 —手続きが暮らしに寄り添う時代へ
- 司法書士が直面する情報提供の葛藤 ―相続人の要望と秘密保持義務のはざまで―
月別アーカイブ
- 2026年1月 (2)
- 2025年12月 (2)
- 2025年11月 (3)
- 2025年10月 (2)
- 2025年9月 (1)
- 2025年8月 (2)
- 2025年7月 (1)
- 2025年6月 (1)
- 2025年5月 (1)
- 2025年4月 (2)
- 2025年3月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (1)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (2)
- 2024年7月 (3)
- 2024年3月 (3)
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (14)
- 2013年6月 (5)
- 2013年5月 (2)
- 2013年4月 (2)
- 2013年3月 (3)
- 2013年2月 (6)
- 2013年1月 (2)
- 2012年12月 (7)
- 2012年11月 (9)
- 2012年10月 (9)
- 2012年9月 (6)