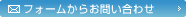Q&A
2023年12月4日 月曜日
“高齢化と株式会社の未来:行方不明株主と廃業・解散の課題”
「少数株主から株式を買い取りたいが行方不明の人がいる。どうしたら良いか」という相談がありました。相談者は株式会社の創業者オーナーで、高齢のため引退したいと考えていますが、後継者がいないため、会社を売るか廃業するかを検討していました。過去に従業員に会社の株を与えていたこともあり、株が分散していました。行方不明の株主は、何十年も前に退職した従業員で、存命か否かもわからない状況です。
行方不明の株主がいる状況でのM&Aは、買い取る側としては好ましくないでしょう。そのまま廃業して解散しても、残った財産は株主への配当(残余財産の分配)となりますので、行方不明の株主への配当金は供託され、恐らく長く眠ることになるでしょう。
株式の譲渡などにより株主が変わった場合、新しい株主は会社に株主名簿の書換を請求する必要があります。株主は、株主名簿に自分の名前が記載されていないと、自分が株主であることを会社に主張することができません。よって、株主の行方不明などにより株主総会の招集通知が届かなかったとしても、株式会社は株主名簿の株主を自社の株主として扱えば良いので、通常の業務・運営に影響はありません。
ただし、株式を買い取るとなると、実際の株主を把握しないと買い取ることはできません。平成2年の商法改正までは、会社設立時に発起人が7名以上必要だったことから、今でも名義株や株式の分散の問題は残っていますが、その解決策として、①所在不明株主の株式の競売、②特別支配株主の株式等売渡請求、③株式併合の3つの方法があります。
①は、所在がわからない株主の株式を競売にかけることができます。ただし、その株主への通知が5年以上到着していない必要があります。株主総会を毎年開催している会社であれば、この前提が起きうる可能性がありますが、中小企業の多くは株主総会を開催していないので、この方法は難しいでしょう。
②は、総株数の90%以上を持つ株主が少数株主に売渡を請求できますが、請求するには単独で90%以上を持っている必要があります。経験則で言うと、100%持っている株主は多く見られますが、単独90%というケースはあまりないようです。株主総会の特別決議が3分の2以上の賛成であり、3分の2が1つのラインとしてあるためかもしれません。
③は、株式を併合(10株を1株に併合など)によって、少数株主を1株未満の株主にすることができます。1株未満となった株式は任意売却か競売で処理されます。ただし、全ての株式が同率で併合されるため、全体のバランスを見る必要があります。
東京商工リサーチによれば、2020年に全国で休廃業・解散した企業は4万9,698件(前年比14.6%増)で、2000年に調査を開始して以来最多を記録しました。休廃業・解散した企業の代表者の年齢別では70代が最も多く41.7%を占めていました。
この数年、解散登記の依頼が増えていますが、今後複雑な廃業・解散が増える可能性があると感じた一件でした。
投稿者
最近のブログ記事
- 司法書士の横領事件から考えること ― 信頼と制度、そして人間の現実 ―
- 不動産登記に詰め込まれる社会 ――増え続ける情報と現場の現実
- 静かな循環の中で― 年の終わりに、司法書士としての感謝を胸に ―
- 対立がなぜ起きるのかをAIに聞いてみた―箱を回して世界を見る―
- 土地と安全保障──日本における防衛目的の土地利用をめぐって
- 国籍記載を義務化へ ―― 日本の不動産市場と経済安全保障の新しいかたち
- 信じる者は救われ…ないかもしれない ー広告社会をAIで透かして見た日常ー
- 時代の波と事業の終焉:2025年ピーク後の日本の「事業の出口」
- 公正証書のデジタル化が始動 —手続きが暮らしに寄り添う時代へ
- 司法書士が直面する情報提供の葛藤 ―相続人の要望と秘密保持義務のはざまで―