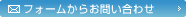Q&A
2023年12月6日 水曜日
“自筆証書遺言書保管制度:安心と円滑な相続のための重要なステップ”
2020年から自筆で作成した遺言書の保管を法務局が行う「自筆証書遺言書保管制度」が導入されています。この制度は、遺言書の紛失、消失、改ざん、隠匿のリスクを減少させることを目的としており、遺言者の死後、法務局が相続人に遺言書の保管を通知することで、円滑な相続を促進します。

**遺言者の手続き**
遺言者は、自筆で作成した遺言書を法務局(遺言書保管所)に預けることができます。この際、遺言書の保管申請を行い、後に必要に応じて遺言書の閲覧や返還を請求することが可能です。
**相続人の手続き**
相続人や受遺者、遺言執行者などは、遺言書保管所に対して遺言書の閲覧を請求することができます。これにより、遺言書の内容を確認し、相続手続きを進めることが可能になります。
**保管制度のメリット**
この制度の最大のメリットは、家庭裁判所による遺言書の検認が不要になることです。これにより、相続手続きの簡略化と迅速化が図られ、遺言書に関する法的な安全性が高まります。
**手数料について**
遺言書の保管申請には、1件(遺言書1通)につき3900円の手数料が必要です。また、保管された遺言書の閲覧を請求する際には、モニターでの閲覧が1回につき1400円、原本の閲覧が1回につき1700円の手数料がかかります。これらの手数料は遺言者や関連する相続人に適用されます。
**まとめ**
遺言書保管制度は、遺言書に関するリスクを減少させ、相続手続きをスムーズに行うための重要な仕組みです。自筆証書遺言の作成と保管について、遺言者自身も関係者も、この制度を活用することで、相続におけるトラブルの予防と円満な解決を図ることができます。
投稿者
最近のブログ記事
- 不動産登記に詰め込まれる社会 ――増え続ける情報と現場の現実
- 静かな循環の中で― 年の終わりに、司法書士としての感謝を胸に ―
- 対立がなぜ起きるのかをAIに聞いてみた―箱を回して世界を見る―
- 土地と安全保障──日本における防衛目的の土地利用をめぐって
- 国籍記載を義務化へ ―― 日本の不動産市場と経済安全保障の新しいかたち
- 信じる者は救われ…ないかもしれない ー広告社会をAIで透かして見た日常ー
- 時代の波と事業の終焉:2025年ピーク後の日本の「事業の出口」
- 公正証書のデジタル化が始動 —手続きが暮らしに寄り添う時代へ
- 司法書士が直面する情報提供の葛藤 ―相続人の要望と秘密保持義務のはざまで―
- AIでの文字起こしが成年後見の現場で大活躍