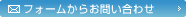ブログ
2025年3月2日 日曜日
メアドに振り仮名?
このコラムで何度か書いているが、日本では「所有者不明土地問題」が深刻化している。登記名義人の死亡後、相続登記がなされないまま長期間放置された結果、実質的な所有者が分からなくなる土地が全国に増加し、その面積は九州本島の約半分とも言われる。背景には、相続登記が義務化されていなかったこと、そして登記システムに「名寄せ」の機能がないことがある。
こうした状況を改善するため、不動産登記制度の新たな改正が行われた。改正の要点は二つある。
第1に、海外に住所がある日本人が日本国内の不動産の登記名義人となる場合、日本国内の連絡先を登記申請情報として提供することが必要となった。これにより権利移転の際に連絡不能となるリスクを軽減できる。
第2に、登記申請時に検索性向上のための情報として、(1)氏名、(2)氏名の振り仮名、(3)住所、(4)生年月日、(5)メールアドレス、の提出が求められるようになった。生年月日やメールアドレスを集約し、将来的に同一人物の所有不動産をより正確に把握できる名寄せ機能に活かそうという狙いがある。
しかし、この改正には思わぬ波紋が広がった。特に問題視されたのが「メールアドレスに振り仮名を付ける」というルールである。実務の現場では、司法書士たちが強く反発した。理由は単純で、「意味のない手間が増えるだけ」だからだ。現代の司法書士が手書きで登記申請書を作成することは皆無で、Wordなどのソフトを使い、オンラインで申請するのが常識である。そんな中で、メールアドレスにまで振り仮名を付ける必要性を感じる実務家は皆無だった。
正直なところ、「taro.kono@gmail.com」を「タロー ドット コウノ アット マーク ジーメール ドット コム」と打ち込む姿を想像すると、苦笑いがこぼれる。もはや登記というより暗号解読の世界だ。
この混乱に拍車をかけたのが、元デジタル大臣・河野太郎氏のSNSでの一言だった。彼は「法務省、メールアドレスに振り仮名っていったい・・・」と投稿。たったこれだけのコメントが瞬く間に拡散し、司法書士たちの怒りと共感を一気に引き寄せた。河野氏の発言は、意味のない作業にリソースを割く法務省への皮肉であり、まさに現場のモヤモヤを代弁した形である。
結果として、当初の規定は修正され、「手書きの申請に限り振り仮名が必要」との結論に落ち着いた。現代の実務で手書きの申請がほとんど存在しないことを考えれば、この修正は「誰も傷つかない」落としどころとなった。
今回の改正は、所有者不明土地問題の解決を目指した重要な一歩であることに間違いはない。しかし、その裏側では、官僚的な形式主義と現場の合理性が衝突し、SNS世論がそれを一気に拡散するという、現代日本らしい風景が広がっていた。日本の登記制度はまだまだ進化の途中である。

投稿者
最近のブログ記事
- 不動産登記に詰め込まれる社会 ――増え続ける情報と現場の現実
- 静かな循環の中で― 年の終わりに、司法書士としての感謝を胸に ―
- 対立がなぜ起きるのかをAIに聞いてみた―箱を回して世界を見る―
- 土地と安全保障──日本における防衛目的の土地利用をめぐって
- 国籍記載を義務化へ ―― 日本の不動産市場と経済安全保障の新しいかたち
- 信じる者は救われ…ないかもしれない ー広告社会をAIで透かして見た日常ー
- 時代の波と事業の終焉:2025年ピーク後の日本の「事業の出口」
- 公正証書のデジタル化が始動 —手続きが暮らしに寄り添う時代へ
- 司法書士が直面する情報提供の葛藤 ―相続人の要望と秘密保持義務のはざまで―
- AIでの文字起こしが成年後見の現場で大活躍
月別アーカイブ
- 2026年1月 (1)
- 2025年12月 (2)
- 2025年11月 (3)
- 2025年10月 (2)
- 2025年9月 (1)
- 2025年8月 (2)
- 2025年7月 (1)
- 2025年6月 (1)
- 2025年5月 (1)
- 2025年4月 (2)
- 2025年3月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (1)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (2)
- 2024年7月 (3)
- 2024年3月 (3)
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (14)
- 2013年6月 (5)
- 2013年5月 (2)
- 2013年4月 (2)
- 2013年3月 (3)
- 2013年2月 (6)
- 2013年1月 (2)
- 2012年12月 (7)
- 2012年11月 (9)
- 2012年10月 (9)
- 2012年9月 (6)