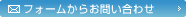2026年1月7日 水曜日
不動産登記に詰め込まれる社会 ――増え続ける情報と現場の現実
最近の不動産登記に向き合っていると、「登記で確認する情報が増えた」という感覚を持つことが多くなった。書類の枚数が増えたというより、社会が抱えるさまざまな問題そのものが、少しずつ不動産登記という制度の中に流れ込んできているように感じられる。
所有者不明土地の問題を背景に、登記名義人をより正確に特定する必要性が高まり、検索用情報の申出が始まった。氏名や住所だけでなく、生年月日やメールアドレスといった情報まで含めて管理し、将来的には名寄せや職権による変更登記につなげていこうという考え方は、すでに実務の前提として受け入れられつつある。
しかし、その流れはそれだけにとどまらない。たとえば旧氏の併記である。婚姻により氏が変わることで、過去の登記名義や社会生活上の履歴との連続性が分かりにくくなるという問題がある。選択的夫婦別姓をめぐる議論が続く中で、「同一人物であることをどう示すか」という課題が、不動産登記の場面にも持ち込まれることになった。
また、外国籍の方が登記名義人となる場合には、ローマ字氏名の確認が必要となる。カタカナ表記との違いや、パスポートに記載された氏名との整合性など、実務の現場では細かな確認作業が欠かせず、その一つひとつに注意を払う必要がある。さらに近年は、外国人による不動産取得をめぐる社会的関心の高まりを背景として、国籍の申出や記載を検討する動きも出てきており、登記で扱う情報の幅は今後も広がっていく可能性がある。
こうして並べてみると、これらは本来、それぞれ別の文脈で語られてきた問題である。所有者不明土地の問題、夫婦同姓・別姓をめぐる議論、外国人問題。いずれも日本社会が抱える重要な課題だが、不動産登記の現場では、それらが一つの登記申請の中に同時に現れることになる。
登記名義人を「誰であるか明確にする」という一点に向かって、社会のさまざまな問題が折り重なるように集約され、その結果として、提供される情報の量は確実に増えてきた。確認事項も、依頼者への説明も、入力やチェックの工程も増え、司法書士の負担が大きくなっているのは事実であるし、同時に法務局の審査や管理の負担もまた、確実に増している。
もっとも、これらの制度は、社会課題の解決を目的としている作られている。社会が抱える複雑な課題に対して、登記制度としてどのように向き合うべきか、その試行錯誤の結果が、現在の制度の姿なのだと思う。
不動産登記は、単なる権利関係の記録ではない。その時代が抱える不安や課題を、静かに引き受け、整理し、形にしていくための器でもある。社会の変化に振り回されながらも、最終的にはそれを整合させ、将来に残していく。その役割を、司法書士と法務局は、日々の実務の中で黙々と担っている。
投稿者 | 記事URL