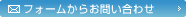Q&A
2023年12月8日 金曜日
行方不明の共有者:所在等不明共有者の不動産の持分の取得
行方不明になった共有者が持っている土地やビルの持分をどうするか、という問題を解決するための法改正がありました。新法では共有者は裁判所の決定を経て、行方不明の共有者が持っていた不動産の持分を取得できます(改正民法262の2)。なお遺産の共有の場合には、相続開始から10年経たないと、この方法は使えません。
申立てをするには、まず証拠を提出し、時価相当額の金銭を供託し、裁判で持分の取得を求めます。行方不明者については、申立人が登記簿や住民票などで必要な調査をして、裁判所がその人の所在が不明であると認める必要があります。
他の共有者については、申立人以外でも、所定の期間内であれば、別途持分取得の裁判を申し立てることができます。もし申立人が複数いる場合は、各申立人が持分割合に応じて、行方不明者の持分を按分して取得することになります。
持分の取得時期に関しては、申立人が裁判の確定時に持分を取得します。これに関しては、3か月以上の異議届出期間を経過する必要があります。
行方不明の共有者は、その持分を取得した共有者に対して時価相当額を請求できます。これは実際には供託金から支払われ、もし差額がある場合には、別途訴訟を起こして請求することもできます。
所在不明者や申立人以外の共有者が異議を申し立てることも可能です。もし所在不明者が異議を申し立てて所在が判明した場合、裁判の申立ては却下されます。また、異議届出期間が満了する前に共有物分割の訴えが提起され、異議の届出があれば、その訴訟が優先され、持分取得の裁判の申立ては却下されます。
投稿者
最近のブログ記事
- 司法書士の横領事件から考えること ― 信頼と制度、そして人間の現実 ―
- 不動産登記に詰め込まれる社会 ――増え続ける情報と現場の現実
- 静かな循環の中で― 年の終わりに、司法書士としての感謝を胸に ―
- 対立がなぜ起きるのかをAIに聞いてみた―箱を回して世界を見る―
- 土地と安全保障──日本における防衛目的の土地利用をめぐって
- 国籍記載を義務化へ ―― 日本の不動産市場と経済安全保障の新しいかたち
- 信じる者は救われ…ないかもしれない ー広告社会をAIで透かして見た日常ー
- 時代の波と事業の終焉:2025年ピーク後の日本の「事業の出口」
- 公正証書のデジタル化が始動 —手続きが暮らしに寄り添う時代へ
- 司法書士が直面する情報提供の葛藤 ―相続人の要望と秘密保持義務のはざまで―